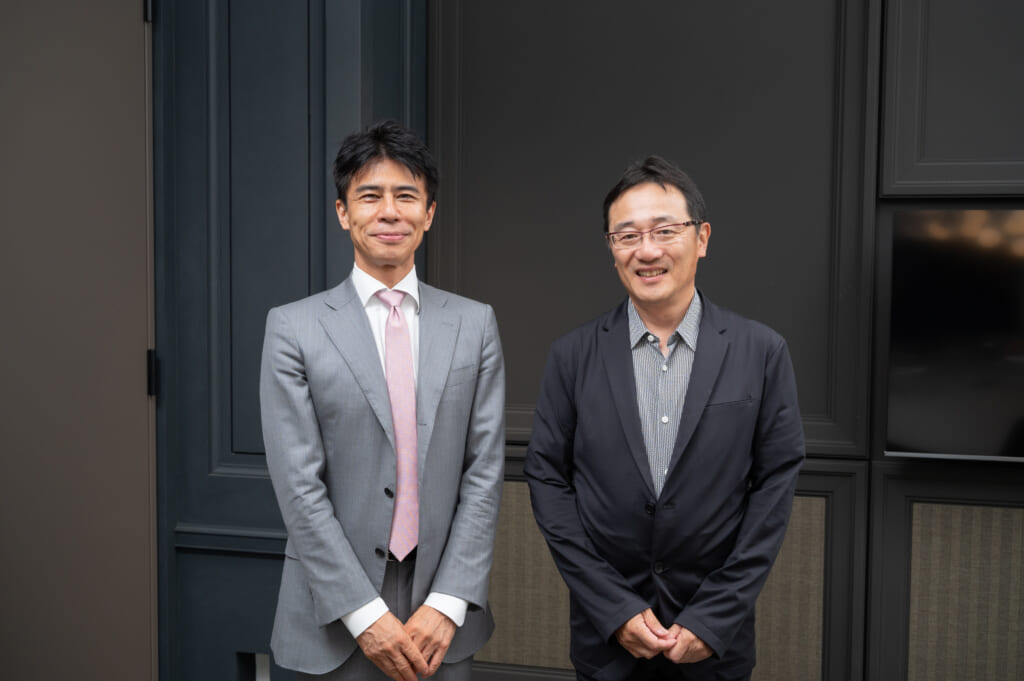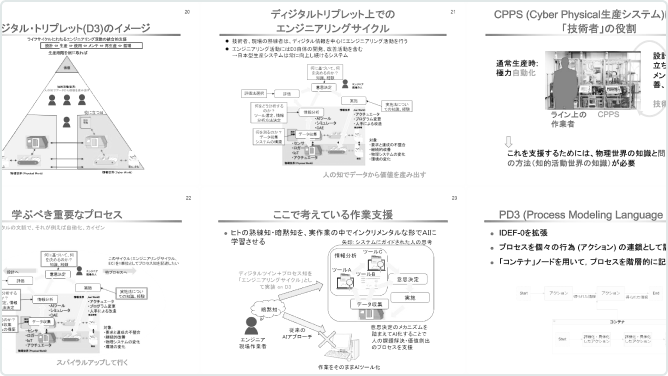【第6回後編】弁護士法人内田・鮫島法律事務所代表パートナー/弁護士・弁理士 鮫島正洋
- 対談連載『リーダーのアタマのナカ』
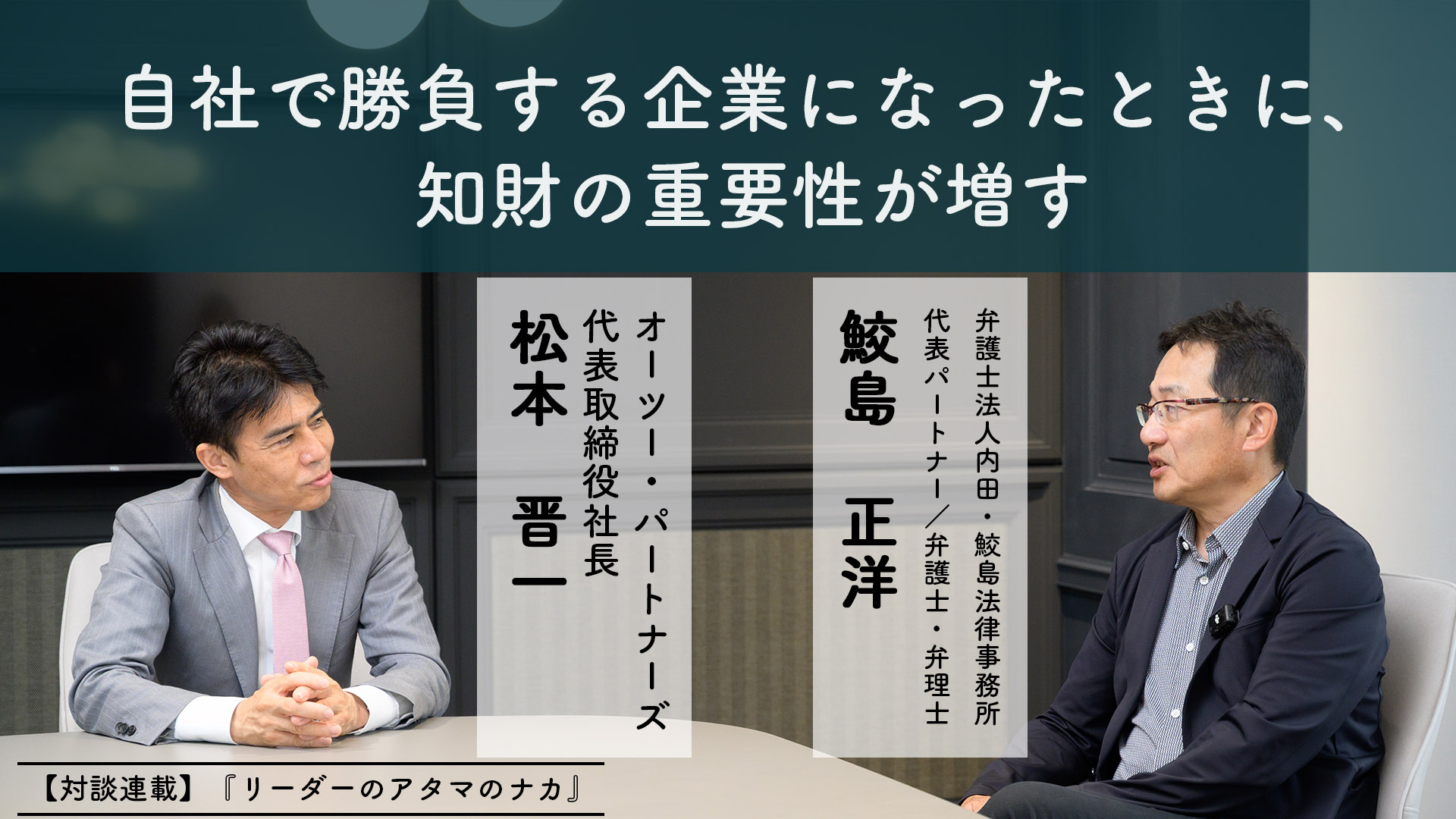
目次
誰もやらないから、私たちが動く。製造業に革新をもたらす、国家レベルの挑戦
オーツー・パートナーズ代表取締役社長・松本晋一が、日本の製造業をより元気にするヒントを求めて各界のキーパーソンに話を聞く対談連載『リーダーのアタマのナカ』。前編に続き、弁護士・鮫島正洋氏をお迎えします。後編では、オーツーが掲げる「GCT(Global Core Top)」の構想や、日本の製造業がこれからどう変わっていけるのかについて、両者の視点からじっくり語り合いました。
「これは、一緒にやらなければいけないな」と思った

松本:2025年4月から、鮫島さんにはオーツーの社外取締役をお願いしています。ご就任をお願いした理由はいくつかありますが、まず何よりも、私たちが強く共感したのはその姿勢です。「下町ロケット」の神谷弁護士のように、大企業・中小企業を問わず、信じた道をまっすぐに歩まれる姿に、深く心を動かされました。オーツーもまた、信念を持って事業を進めてきたので、そのマインドに強い共通点を感じたんです。もう一つは、鮫島さんが技術に精通されていること。私たちも、製造技術に特化したコンサルティングを続けてきた。だからこそ、鮫島さんとご一緒すれば、大きなシナジーが生まれるのではないかと考えています。
鮫島:実は、他社さんからも、社外「監査役」のお話は何度かいただいていたのですが、私には向いていないと、ほとんどお断りしてきたんです。でも今回は、戦略に深く関われる社外「取締役」というお話だったので、お引き受けしようと思いました。手法は違いますが、私たちは知財や法務の立場から、オーツーさんは実務や現場の視点から、中小企業を支援しています。目指すゴールが同じなら、手を組んだ方がいい。
松本:ありがとうございます。さらに言えば、生成AIの急速な進化に、強い危機感も抱いています。私たちが圧倒されている間に、日本の技術や知財が、どんどん吸収されてしまうのではないか。そんな不安があるんです。だから、知財に精通した鮫島さんがそばにいてくださることは、本当に心強いです。一方で、ただ恐れるだけでなく、生成AIを積極的に活用しながら、新たなビジネスモデルの構築にも挑戦していきたいと考えています。そうした取り組みにおいても、知財の視点からアドバイスをいただければ、非常にありがたいと思います。
鮫島:うちは製造業だけではなく、バイオなど他の技術分野にも関わっていますが、「日本を元気にする」「日本の未来を豊かにしたい」という想いは、オーツーさんとまったく一緒です。
松本:当社のパーパスをお伝えしたときに、鮫島さんが「うちもまさにそれを目指しています」って言ってくださったのは、本当にうれしかったですね。
鮫島:あのときに、「これは、一緒にやらなければいけないな」と、心の底から思いました。
自ら輝ける “GCT”企業を創出し、製造業の構造に変革を
松本:改めてお話させていただきますが、オーツーでは、「GCT(ジー・シー・ティー)企業の輩出に貢献する」というミッションを掲げています。GCTは「Global Core Top(グローバル・コア・トップ)」の略で、「しっかりとした強み(=コア)」を持っていて、狙いを定めた市場で独自の価値を出し続けることができる企業。そして、その価値がグローバル市場でも通用する企業です。私たちはコンサルティングを通じて、日本の企業をこの「GCT」へ導くことを目指しています。
鮫島:なるほど。核となる強みを持って、自分たちの土俵で勝負している企業、というイメージですね。
松本:そうですね。そして、ここでいう「コア」というのは、技術だけに限りません。製造工程や営業力、アフターサービスなど、バリューチェーン全体の中で、自分たちならではの強みを持っている企業です。たとえば、キーエンスのように自社工場を持たず、設計と販売に特化して成果を出している会社もあれば、「部品交換の依頼があれば、確実に24時間以内に届ける」という、保守体制の強さが売りの会社もあります。それぞれ強みや状況が異なるため、私たちの関わり方もすべて“オーダーメイド”になります。
鮫島:ただ頑張っているというだけではなく、「うちはここが強みです」とはっきり言える企業ということですね。
松本:まさに、そういう“自分たちの軸”をしっかり持っている企業が、私たちが理想とするGCTの姿です。これは中小企業に限った話ではありません。むしろ、大企業の中でも、各事業部がそれぞれGCTのような存在になるべきだと考えています。理想的な大企業とは、いくつものGCT的な事業部が集まって、全体として一つの大きな価値を生み出している状態ではないかと。
鮫島:なるほど。
松本:そしてGCTを増やすことで、最終的に目指したいのは、「日本の産業構造そのものを変えること」です。いまの日本の製造業には、いまだに“ピラミッド型”の構造が根強く残っていますね。完成品メーカーが頂点にいて、その下に多くの下請け企業が連なっているという状態。さらに、価値や機能の多くが首都圏に集中し、地方との間には大きな格差も生まれている。
鮫島:たしかに。階層が固まっていて、上に依存せざるを得ない企業もまだまだ多いですよね。
松本:この従来の構造から脱却して、これからの時代には、各企業が自らの強みを活かしながら自立し、対等な関係でつながっていくような仕組みが求められます。私たちはこの新しい形を、「ミルキーウェイ型(天の川型)」の産業構造と呼んでいます。
鮫島:ミルキーウェイ、天の川ですか?
松本:はい。天の川のように、各所に“きらぼし”(=GCT企業)が輝いているイメージから名付けました。ピラミッド型のような「上と下」ではなく、領域ごとにコアとなる企業が存在し、対等につながっている構造です。サプライチェーンに序列がなく、会社の大きさも関係ない。「どんな価値を出しているか」が重視される。そういうGCT企業が、設計・製造・保守などが各工程に存在している状態ですね。
鮫島:なるほど、それぞれの企業がキラリと光る核を持っているから、全体として輝く“天の川”になるわけだ。上下がなく、自立と連携で成り立つ仕組みは、まさにこれからの時代に求められる形かもしれません。
松本:そうなんです。私たちは、この「ピラミッド型」から「ミルキーウェイ型」への転換を、単なる理想論や憧れで終わらせたくない。本気で、日本の産業の未来にしていくつもりです。
鮫島:単に「技術に強い企業を増やそう」ということではなくて、社会全体の構造そのものに働きかける、ということですね。
松本:その通りです。そしてもう一つ、大切にしたいのが「地方創生」です。GCTのような企業を、首都圏だけでなく、地方にも増やしていきたいと考えています。「東京本社の子会社が地方にある」という形では、地域に根ざした意思決定や経済循環は生まれにくい。だから、地元で主体的に価値を生み出せるGCT企業を育てて、地方から変革を起こしたいのです。そうなれば、地域の経済圏そのものが大きく変わるはずですから。その実現に向けて、私たちは、「ことを起こす人」や「突破できる人」、つまり変革をリードする人材をどんどん輩出していくような会社でありたいと思っています。地方から産業を変え、構造を変え、人を育てる。これが、私の考えるこのミッションの核心です。
そこにも、ぜひ鮫島さんのお力をお借りできたらと思っています。鮫島さんは、我々のGCTという考え方をどう捉えましたか?また、どんなふうに関わっていけそうだと感じていますか?鮫島さんのお考えを、改めてお聞かせいただけたらうれしいです。
自社で勝負する企業になったときに、知財の重要性が増す
鮫島:ありがとうございます。このGCTという考え方には非常によく共感できます。私たちもこの10年、知財の分野で、かなり近いテーマに取り組んできたつもりですから。
頂点に大手の完成品メーカーがいて、その下に系列の部品メーカーや中小企業が並ぶような、いわゆる「ピラミッド型」の構造は、特に中部地方で色濃く見られてきました。でも最近では、そこに変化が起き始めているんです。というのも、ある時期を境に、下請け側が「自立」に向けて動き出したからです。そのきっかけとなったのが、民主党政権時代の急激な円高です。1ドル80円台にまでなったあの頃、大手メーカーが「国内生産ではコストが合わない」と判断し、生産拠点や調達先を次々と東南アジアへ移し始めました。
松本:ありましたね。あのとき、現場の中小企業は相当ショックを受けていたと思います。
鮫島:そうなんです。長年そのメーカーに尽くしてきた中小企業は、「これまで、言われた通りにコストを抑え、品質も守ってきたのに、いざとなったら切り捨てるのか」と反発の声を上げたんですね。そこから生まれたのが、「下請け一本では限界がある。これからは、自分たちの強みを活かして、自社製品を持とう」という動きです。中部地域では、こうした企業が少しずつ増えてきています。
ここで大きな鍵になるのが、「知財」の存在です。下請けに徹している間は、正直、知財なんて関係ない。むしろ、勝手に特許を出願しようものなら、「何をやっているんだ」と元請けから叱責されかねません。でも、自社で製品を開発し、自分たちの力で勝負しようとした瞬間から、知財の重要性が一気に高まるんです。
松本:自分たちでブランドをつくるなら、それを守る手段も持たないといけない。
鮫島:その通りです。特許をきちんと取っていないと、競合に真似されたり、抜かれたりする可能性があります。だからこそ、知財の知識や戦略が必須になる。私はこの10年ほど、こうした動きを後押しするために、中部地区での知財戦略の支援に取り組んできました。まさに今、そうした自立型の中小企業――“きらぼし”のような存在――が、少しずつ増えてきている。それを肌で感じているので、松本さんのお話には本当に共感できました。
松本:ありがとうございます。
鮫島:地方創生のお話も、まさにその通りだと感じました。前編でも触れましたが、私たち法律家も、「東京から弁護士を送り込む」のではなく、「地元の弁護士が地元で対応する」ことが望ましいと考えていますので。
ちなみに、地方に関して興味深い事例があります。中部地区はかなり高い技術力を持つ地域なのに、少し前までは中小企業の特許出願数が少なかったんですよ。
松本:えっ、そうなんですか?
鮫島:これは、おそらく地域全体に根づいていた“ピラミッド型”の産業構造が影響しています。つまり、完成品メーカーを頂点に据えた上下関係の中で、下請け企業が自らの知的財産を主張する機会がなかったことを表しています。一方で、京都はまったく逆の傾向があります。京都の製造業は独自性を非常に大切にしていて、「まねされたら困る」という意識が強く、特許などの知財でしっかり守ろうとする文化が根づいているんです。伝統の町でありながら、新しいものへの感度が高く、知財への意識も非常に先進的。こうした地域文化の違いが、知財戦略にもはっきりと表れていると感じます。
松本:「下請けのときは特許は関係ないけれど、自社で何かをやろうとした瞬間に知財の重要性が増す」という鮫島さんのお話、すごく腑に落ちました。まさに、そうですよね。
鮫島:ただし、下請けが“きらぼし”になるのは、そう簡単じゃないですよね。技術力がある、というだけでは足りない。
松本:はい、そこはやっぱり難しいですよね。
鮫島:下請けのときは依頼書どおりに作って納品すればいいから、マーケティングも販路開拓も必要ありませんが、自社製品を出すならば、自分たちで市場を見て、研究開発のテーマを決め、特許チェックをする必要もある。今までやってこなかったことを、全部やらないといけなくなります。
松本:そうなんですよね。だから私たちは、複数のGCTが互いに連携しながら新たな価値を生み出せるよう、サービスの設計そのものから踏み込まなければならないと考えています。厳しい挑戦ではありますが、そういう共創モデルを一つでも多く実現することが、私たちに課せられた役割です。
そして、この仕組みが実現すれば、たとえば地方にある年商40億円規模の企業を、数百億円規模のグローバル企業へと再生・成長させることも決して夢ではありません。そうなれば、その地域のGDPにも確実にインパクトを与えるはずです。
鮫島:それはまさに、地方創生のど真ん中を突く発想です。本当に意義のある取り組みだと思います。実は、特許庁も長年にわたって「地方創生」を掲げて、知財の側面からさまざまな支援を行ってきたんですよ。でも、私はずっと、「知財だけをやっていても、本当の地方創生にはならないだろう」と感じていました。
松本:たしかに、知財があるというだけでは、企業そのものが大きく変わるわけではありませんよね。
鮫島:おっしゃる通りです。実は、こうした総合的な企業支援を担える部署って、今の官公庁の中にはほとんど存在しないんです。経済産業省でも中小企業庁でもない。やるとしたら各地の経済産業局くらいでしょうか。だからオーツーさんのように、全体を見渡しながら企業を支援できる存在って、ものすごく貴重です。最終的に地方創生が目指すべきところは、GCT的な企業をいかに増やすかということに尽きると思いますので。――こうした切り口で支援しているコンサルティング会社って、他にもあるんですか?
松本:あまり聞いたことがないですね。
鮫島:ですよね。私も聞いたことがない。これは、コンサルティング会社の仕事というより、国の産業戦略としてやるべき取り組みですよ。それくらい重要な観点だと思います。
松本:他のコンサルティング会社がやっているのは、財務戦略を立てたり、資金調達を手伝ったりなど、機能レベルを個別に強化するような支援ですよね。でも私たちは、「企業としてどうあるべきか」というビジョンそのものを提案して、そこに向かって一緒に汗をかくというスタイルでやってきましたので。これは、たぶんかなり珍しいと思います。
鮫島:本当にそうですね。しかも、それを「地域の競争力につなげよう」としているコンサルは、私の知る限りありません。むしろ、行政的な発想に近い。でも、それができる民間の存在は、絶対に必要だと思います。
松本:まさに、そこを一緒にやっていただけたら、と思っています。
鮫島:賛成です。ぜひ、力を合わせて取り組みましょう。
越境と孤独を経て、「何かを託される」瞬間が訪れる

松本: 最後に鮫島さんにお伺いしたいのですが、私は人が成長するうえで「越境」と「孤独」が欠かせないと思っているんです。というのも、私自身、学生時代にバックパッカーとして旅をし、日本人がほとんどいない土地に一人で飛び込んだ経験があります。言葉も文化も違う環境のなかで、居場所を探しながら過ごした時間が、自分を大きく成長させてくれました。そして鮫島さんも、まさに「越境」された方ではないかと。理系から文系へ、つまり技術者から弁護士というまったく異なる領域に挑戦されて、もがきながら自身のスタイルを築いてこられた。そのご経験をふまえて、これからキャリアを切り拓いていく若い世代に、アドバイスをいただけますか?
鮫島:そうですね。私も、これまでにさまざまな「越境」と「孤独」を経験してきました。なかでも特に大きな挑戦だったのが、「法律事務所なのに、技術の分かる人間だけを集める」という試みです。当時は業界内で「そんなの無謀だ」と笑われました。でも実際、中小企業の経営者と向き合えば、最初に出てくるのは技術の話です。その内容が理解できなければ、信頼関係を築くことなんてできません。だから、たとえ周囲からバカだと言われても、やる価値があると確信して進めました。それが、私にとっての「越境」だったのだと思います。
松本:まさに「変革者」ですね。
鮫島: ありがとうございます(笑)。若い世代にも、ぜひ思い切ってチャレンジしてほしいですね。私の時代は何もなかったけれど、今は我々が築いてきたプラットフォームがある。環境は確実に整ってきていると思います。
松本: そういう挑戦をする人って、どういうきっかけでその一歩を踏み出せるんでしょうか。使命感や正義感からくるものでしょうか。
鮫島:うーん、理屈ではなくて、もっとこう、何かに突き動かされるような感覚なんですよね。「お前がやるんだ」と、背中を押されるような…。私自身、そうした運命めいた力が働いたと感じる瞬間がありました。それが、まさに司法試験のときです。合格できたのは、本当に奇跡のようなもので。模試の結果からすると、合格の可能性はせいぜい30%でしたから。仕事を続けながら3年半、挑戦を続けていて、「今年ダメだったら諦めよう」と思っていたんです。そんなときに、準備していた内容が、ピンポイントで試験に出てくるような幸運が何度か重なって、試験が終わった瞬間、「これは受かった」と、直感的に感じました。
松本: それって、「導かれている」って感覚ですよね。私もバックパッカー時代、マラリアにかかったり、コレラになったり、強盗に遭遇したりと、命の危機に4回くらい直面したんです。でもそのたびに生き延びて、「ああ、自分にはまだ果たすべき役割があるんだ」って思ったんです。「生かされたからには、何かを果たさなければ」。そう感じたことが、今の私の志やパーパスに繋がっている気がします。
鮫島:人って一生懸命に生きていると、ある瞬間に「これは自分がやるべきことだ」と思えるような、ある種の“啓示”みたいなものが降りてくる瞬間があるのかもしれませんね。今日はかっこいい話しかしていませんが(笑)、もちろん、いろいろ紆余曲折あって――嫌なことも、つらいこともあった。でも、「私は何かを託されたのだから、やらなければ」という信念はずっと変わらずに20何年間やってきました。
松本:そういうことを、「運命」や「使命」と呼ぶのかもしれませんね。
鮫島:万人にそういうことが訪れるかというと、正直分かりません。ただ、もし「何かを与えられた」と感じたなら、それを受け止めて前に進む。そういう人が結果的に、自分の軸を持って歩んでいけるのではないでしょうか。