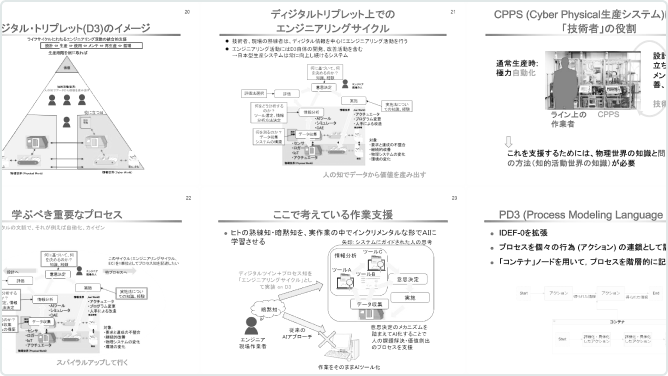【第6回前編】弁護士法人内田・鮫島法律事務所代表パートナー/弁護士・弁理士 鮫島正洋
- 対談連載『リーダーのアタマのナカ』

目次
エンジニア出身「下町ロケット」の弁護士が切り拓いた“技術法務”の道
製造業の未来を照らすヒントを探るため、オーツー・パートナーズ代表取締役社長・松本晋一が、各界の第一線で活躍する変革者に迫る対談連載『リーダーのアタマのナカ』。今回ご登場いただくのは、知財戦略のエキスパートとして、数多くの中小企業を支えてきた弁護士・鮫島正洋氏です。池井戸潤氏の直木賞受賞作『下町ロケット』に登場する“神谷弁護士”のモデルとしても知られる同氏は、2025年4月よりオーツー・パートナーズの社外取締役に就任しました。今回は、そんな鮫島氏にご自身のキャリアの軌跡、そして今後の展望についてお話を伺います。
幼少期は人見知り。夢中になった遊びは「ルールメイキング」

松本:鮫島さんは、東工大(現・東京科学大学)をご卒業されていますね。理系出身でありながら、現在は弁護士として活躍中というユニークなご経歴をお持ちですが、もともと、なぜ理系の道に進まれようと思ったのですか?
鮫島:理系を選んだ理由は、単純に暗記が苦手だったからです。物理のように論理的に考えて解く科目のほうが面白くて、「自分は理系の人間なんだ」と思っていました。ところが、東工大に入ってすぐ、それが思い込みだったと気づかされました。同級生たちは、小さい頃から電子工作やラジオ作りに夢中だったような人ばかり。一方の私はというと、夏休みの工作ですら面倒で仕方がないタイプだったんです。
松本:なるほど。じゃあ、小さい頃から理系一直線、という感じでもなかったんですね。どんなお子さんだったんですか?
鮫島:いやあ…相当な人見知りだったようです。おばが、「この子は将来、社会でやっていけないんじゃないか」と心配していたとか。今でもそうですよ。立食パーティーなどはほんと苦手(笑)。グループで話しているところに割って入って名刺交換とかは、絶対できません。
松本:鮫島さんが人見知りというのは意外ですね。幼少期は、どんなことをして遊んでいました?
鮫島:ちょっと変わっているかもしれませんが、「自分でルールを考えて創る」ようなことが好きでしたね。当時は今のようなコンピューターゲームなんかなかったので、紙の上で自作のゲームを作って遊んでいました。たとえば、画用紙に野球のグラウンドを描いて、小さな紙を指ではじいて「ここに入ったらヒット、こっちはアウト」とか。子どもながらに、「こういうルールを考えるのは楽しいな」と思っていました。
松本:へえ、面白いですね。自分からルールや仕組みを考えるっていうのは、鮫島さんの今のお仕事にも通じるところがありそうです。
鮫島:そうですね、結構つながっているかもしれません。実は、飲み会の幹事をやるのも大好きなんです(笑)。料理を考えたり、ちょっとした演出を工夫したり。
松本:人を楽しませることがお好きなんだ。その気持ちって、経営においても大切ですよね。職場には楽しさがなければ、従業員のモチベーションが続かないし、辞めてしまう人も出てくる。“楽しさをどう設計するか”は、組織づくりの要だと思っています。
鮫島:たしかに。楽しさって、ただ面白おかしく盛り上げることじゃなくて、共感の上に成り立っているものなんですよね。「どうすれば気持ちよく働けるか」「どうすれば前向きになってもらえるか」を考えて工夫する。そういう場づくりは、たぶん好きなんだと思います。
松本:すごく分かります。「これが正解だから」と押しつけられたことをやってても、楽しくなんて働けませんよね。
鮫島:ええ。そういう部分にトップが鈍感だと、いい経営はできないと思います。「売上さえ伸びればいい」ってスタンスで、いくら待遇だけを良くしても、共感できなければ人は動かない。やはり、気持ちが伴ってこそですよね。
工学から法の道へ。異色のキャリアが生んだ知財のスペシャリスト
松本:「理系は自分の道ではない」とうっすら気づかれながらも、大学をしっかり卒業されたのはすごいですね。
鮫島:いやあ、学生時代は本当に自由奔放で。授業にはほとんど出ず、実験とレポートだけでなんとか単位を取っていましたよ(笑)。テストの平均は60点合格ラインの63点くらいで、教授からは「こんな綱渡りで進級する学生は珍しいよ」と笑われました。卒業後は、その教授のご縁で、フジクラという会社に拾っていただいたんです。
松本:フジクラは、電線・通信インフラ・電子部品などを手がける最大手メーカーのひとつですね。入社されてからは、どんな感じだったんですか?
鮫島:いや、それがですね、エンジニア職として採用されたのですが、半年も経つと、「やはり自分には向いていない」と思うようになりました。東工大に入学したときと似たような感覚ですね。それでも、採用していただいた以上「できるところまでやってみよう」と思って続けた結果、気が付けば7年半が経っていました。
松本:それだけ続いたということは、得られるものもあったのでしょうね。
鮫島:ええ。フジクラでの7年半は決して無駄ではなく、大きな財産になりました。新規の電線の開発・製造ラインを担当し、製造のみならず、材料の調達から品質保証まで、ほぼすべての工程をやらせてもらって、「ものづくりとはこういうものか」と実感する日々でした。今、弁護士として技術者の方々と向き合うときに、当時の経験が生きていることを感じます。
松本:なるほど。それでも、やっぱり長く続けるのは難しかったですか?
鮫島:そうですね。この仕事を一生続けていくのは厳しいな、と感じていました。ただ、そこで場当たり的に次の仕事を選んでしまっていいのか、という気持ちもあって、「どうせなら、自分の軸になるような“手に職”をつけよう」と思い始めたんです。
松本:そこで資格取得を目指されたんですね。
鮫島:はい。理系の知識を活かしやすい、弁理士の資格を取ることにしました。特許法を始めとした知的財産法の勉強を始めると、驚くほど自然に頭に入ってくることに、驚きましたね。それまで、技術の勉強にはあんなに苦労していたのに。やっぱり人は、向いていることならスッと馴染むものなんです。実は、私の家系は文系寄り。祖父も、海事法専門の弁護士で、法律事務所を営んでいたと聞いています。
松本:おじいさまも専門特化型の弁護士だったんですか!やはり血は争えないですね。
鮫島:ええ、自分でもそう思います(笑)。弁理士の資格を取った後はIBMに転職して、新たなスタートを切りました。ただ、しばらくすると「このまま年齢を重ねたときに、ずっと技術の最前線でやっていくのは難しいかもしれない」と思うようになったんですね。同時に、ビジネスへの関心もどんどん強くなっていきました。それで、「いっそ弁護士になろう」と考えたんです。弁理士としての経験も活かせるし、ライセンス交渉などを通じて、ビジネスにも関われる。面白いかもしれない、と。
松本:それで、司法試験に挑戦されることになったのですね。弁理士として働きながらのご決断だったとすると、かなり大変だったんじゃないですか?
鮫島:大変でした。さすがに一発合格は難しく、3回目でなんとか通った感じです。
松本:それでも、やり切ったのはすごいですね。
鮫島:もう二度とやりたくないですけどね(笑)。
中小企業を支えることで、社会に貢献する。技術法務の原点
松本:司法試験に合格してからは、そのまま独立されたんですか?
鮫島:いえ、最初は大手の法律事務所に入りました。ただ、訴訟や企業法務といった一般的な弁護士業務より、「技術に関わる仕事がしたい」という思いが強くて。いろいろ模索する中でたどり着いたのが、知財分野における中小企業の支援でした。というのも、大企業には法務部や知財部といった専門部署がありますが、中小企業にはそうした体制が整っていないことが多いんです。けれど、契約や特許といった知財は、どんな企業にとっても極めて重要です。だったら、「自分がその役割を担おう」と考えるようになったんです。
松本:なるほど。
鮫島:技術力のある企業に対してヒアリングをして特許を取得し、契約面もきちんと整備する。その結果、新しい製品が世の中に届けられ、ビジネスの原動力になっていく――。これはまさに、社会への貢献そのものです。「自分は、こういう仕事がやりたかったんだ」と、一気に視界が開けたような気持ちでした。
松本:そういったお仕事を、事務所の中で少しずつ実践されていたわけですね。
鮫島:はい。当時の事務所のボスも、私のやっていることを「面白い」と言って、かなり自由にやらせてくれました。でもそのうち、中小企業の案件がどんどん増えてきて、さすがに一人では手が回らなくなりまして。「新しく人を雇うなら自分でやるしかない」となり、独立することになったんです。
松本:なるほど。独立後はすぐに軌道に乗ったんですか?
鮫島:そうですね。本当にありがたいことに。これは後から聞いた話なのですが、私が独立する際、それまで私が担当していたクライアントに、ボスが「鮫島が独立するので、よければ今後も彼に任せてあげてください」と声をかけてくれたそうなんです。そのおかげで、独立直後から仕事をいただける環境が整っていました。いわば、下駄を履かせてもらったようなスタートでしたね。そのときのお客様とは、今でも変わらずお付き合いが続いています。
松本:それは本当に心強い後押しでしたね。そして今では、技術に特化した事務所として、35名体制にまで成長されている。
鮫島:そうですね。技術に特化した法律事務所としては、日本の最大手だと思います。最近では、経産省や特許庁といった政府の委員会に関わらせていただく機会も増えて、日本の産業や社会の未来に貢献できているというやりがいも感じています。また、若手が着実に育ってきているのもうれしいですね。今は「人を育てる」という役割そのものにも、大きな喜びを見出しています。
松本:次の世代にバトンをつなぐフェーズに入ったのですね。
鮫島:はい。私たちは今の仕事を「技術法務」と呼んでいますが、2000年代の初め頃までは、この分野に精通した専門家――つまり、今の私たちのような立場の人間は、ほとんどいませんでした。しかし、日本は世界に誇れる優れた技術を持っている国です。だからこそ、技術を正しく理解し、法的に支える専門家がもっといてもいいはず。そう思って、自分がこの分野を立ち上げようと決意しました。そして、この取り組みをしっかりと根付かせていくには、志を同じくする仲間を増やし、ある程度の規模にすること、そして次の世代を担う人材を育てることが不可欠です。35人では、まだまだ足りないと感じています。
松本:どれくらいの人数が必要だと見ていますか?
鮫島:マーケットの実情を考えると、今後は100人から300人ほどの専門家が新たに必要になります。中でも重要なのは、東京だけでなく、全国各地で「技術法務」を担ってくれる弁護士を見つけ、それぞれの地域に根づかせていくこと。地域に密着し、信頼関係を築ける体制づくりが欠かせません。
技術法務を全国に根付かせる、“総本山”の覚悟

松本:地域密着でやる必要があるのはなぜですか?東京で人材を育てて、全国に送り出すという形では不十分でしょうか。
鮫島:それだけでは、やはり限界があります。というのも、東京の弁護士が地方に進出してくることに、抵抗感を持たれることも少なくないからです。地元で築いたネットワークに影響が出るのではないか、という懸念があるのだと思います。そうした中で、地元の企業と信頼関係を築いていくのは容易なことではありません。だからこそ、地域に根差した技術法務の担い手が、各地に必要なんです。
松本:やはり、「地元は地元で守っていきたい」という意識が強いんですね。
鮫島:そうですね。たとえば、九州の企業は九州の弁護士が、北海道の企業は北海道の弁護士が対応する。その方が、その地域の文化や商習慣にも精通していますし、地元との信頼関係も築きやすい。私たちの事務所は、その全国ネットワークを支える“総本山”のような存在であれたらいいなと。そんなビジョンを描いています。
松本:仮に、全国にパートナーとなる仲間が増えていった場合、鮫島さんたち“総本山”としての役割とは、具体的にどんなものになるのでしょうか?
鮫島:ひとつは、新しい実務の開発です。
松本:新しい実務、というのは?
鮫島:私たちが今やっていることは、「技術法務」という広い領域のほんの一部にすぎません。たとえば、金融工学的な知識が求められる場面など、対応すべき分野はまだまだ数多くある。そうした新たなニーズに応える実務を開拓していくことは、“総本山”としての大切な役割だと考えています。
松本:なるほど。ただ、その立場を維持し続けるのって、簡単なことではありませんよね。弁護士は資格の上ではみな対等ですが、東京の事務所が地方より「上」という空気が、知らず知らずのうちに生まれてしまう可能性もあります。真に対等な関係で連携できるコミュニティやエコシステムを築くには、“総本山”となる存在に、ある種の求心力が必要だと思うんです。つまり、他にはない“強み”のようなものですね。その強みは、どこにあるとお考えですか?
鮫島:これは少し専門的になりますが、技術系の弁護士の仕事は大きく2つに分かれます。ひとつは、大企業向けの特許訴訟対応です。たとえば、日本製鉄がトヨタを訴えたようなケースですね※。もうひとつは、中小企業やスタートアップ向けの経営支援。こちらはオーツーさんの実務にも通じるような、コンサルティング要素の強い仕事です。そのどちらかをやっているところはありますが、この両方に本気で取り組んでいるのは、私たちの事務所のほかにはありません。
※ 日本製鉄は2021年、トヨタおよび中国・宝山鋼鉄に対し、特許侵害を理由に東京地裁へ提訴。
松本:その両方に取り組むことで、パートナーとなった弁護士にはどんなメリットがありますか?
鮫島:最大のメリットは、訴訟の現場で実践的なスキルを磨き続けられることです。特許訴訟は、弁護士同士が本気でぶつかる“勝負の場”であり、高度な判断力や表現力が求められます。その場数を踏んだ弁護士が、企業の経営支援や知財戦略にも関われる。この実務と戦略の両立こそが、私たちの仲間として活動する中で得られる、大きな価値になります。実は、地方の弁護士って、特許訴訟に携われるチャンスがあまりないんですよ。
松本:それはなぜですか?
鮫島:本格的な知財部門を持つ裁判所が、東京と大阪にしかないからです。実際、特許訴訟を本格的に扱える法律事務所は、全国でも20に満たないのが現状。その中で、私たちは間違いなくトップクラスに入る事務所です。もし、地方で中小企業を支援している弁護士が訴訟対応を求められたときには、私たち“総本山”がしっかり支えてあげられます。
松本:なるほど。お話をうかがって、“総本山”という言葉が、とても腑に落ちました。
事業継承は熟成である。カレーのように、じっくりと
鮫島:そういえば、ちょっとした自慢なんですが、2020年以降、うちの弁護士35人のうち、ひとりも辞めていないんですよ。
松本:えっ、5年間ゼロですか。それはすごいですね。弁護士の離職率は、かなり高いと聞きますが※。
※一般企業の平均離職率は約15%(厚労省調査)。弁護士業界の正式な統計はないが、若手弁護士の3年以内離職率は30〜50%前後とも言われる。
鮫島:ええ、実際すごく流動性が高い業界です。感覚的には一般企業の2〜3倍はあるんじゃないかな。でも、最初からうまくいっていたわけではありませんよ。独立して最初の5年間くらいは、2人採用して1人残るかどうか…みたいな状態が続いていました。
松本:そこから状況が変わったきっかけって、何かあったんですか?
鮫島:うーん、実ははっきりした理由は分からないんです。自分でも不思議で。
松本:私なりにひとつ仮説があるのですが…最近の鮫島さん、現場の最前線に立つことが少なくなっていませんか?
鮫島:そうですね。もう事業承継のフェーズに入っていますし、意識して自分が一歩引くようにしています。若い人たちに前に出てきてほしいので。
松本:もしかして、「自分が前に出なくても大丈夫だな」と感じるようになったその時期と、人が辞めなくなった時期って重なっていませんか?
鮫島:ああ、たしかに。言われてみれば、そうかもしれませんね。
松本:トップの存在感って、良くも悪くも影響力が大きいですよね。前に出てグイグイ引っ張っているときは、活気はあるけれど、他のメンバーが前に出づらい。でも、少し引いて見守るようになると、次の世代を担うリーダー層が育って、組織に落ち着きや安定感が出てきます。
鮫島:たしかに。カレーってグツグツ煮込んでいるときは熱くて活気がありますけど、火を止めて少し冷ますと、味がじんわり染み込んできますよね。あの感じに似ていますね。トップが一歩引いたときにこそ、深みが出てくる。
松本:その例え、いいですね(笑)。もちろん、創業期には、強いリーダーシップが必要です。でも、ずっとトップが前に出続けるのは相当なエネルギーが要るし、無意識のうちに周囲にプレッシャーをかけてしまうこともある。だからこそ、支える側に回るタイミングになったとき、組織は次のフェーズに進むのかもしれません。
鮫島:そう思います。しかも、トップが一歩引くことで、組織の“進む方向”が変わっていくことがあるんですよね。それって、実はとても大切なことなんですよ。同じ人間がずっと前に立ち続けていると、どうしても過去の成功パターンにとらわれてしまいますから。
松本:うん、それは本当に共感します。
鮫島:時代に合わせた新しいやり方を模索していくには、若い世代に任せることが大事です。今の私は、「必要なときにだけそっと舵を取る」くらいの距離感がちょうどいい。
松本:トップがすべてをコントロールするのではなく、任せて、見守って、必要なときだけ支える。それが、強い組織をつくる一番の近道かもしれませんね。
鮫島:実際、いま多くの中小企業が事業承継に悩んでいて、「後継者がいない」「次が育たない」という悩みを本当によく耳にします。でも事業継承は2〜3年で結果が出るものではありません。10年単位でじっくりと育てていくものなんです。「事業承継は熟成である」という意識を、経営者は早い段階から持っていたほうがいいかもしれませんね。
(後編へつづく)